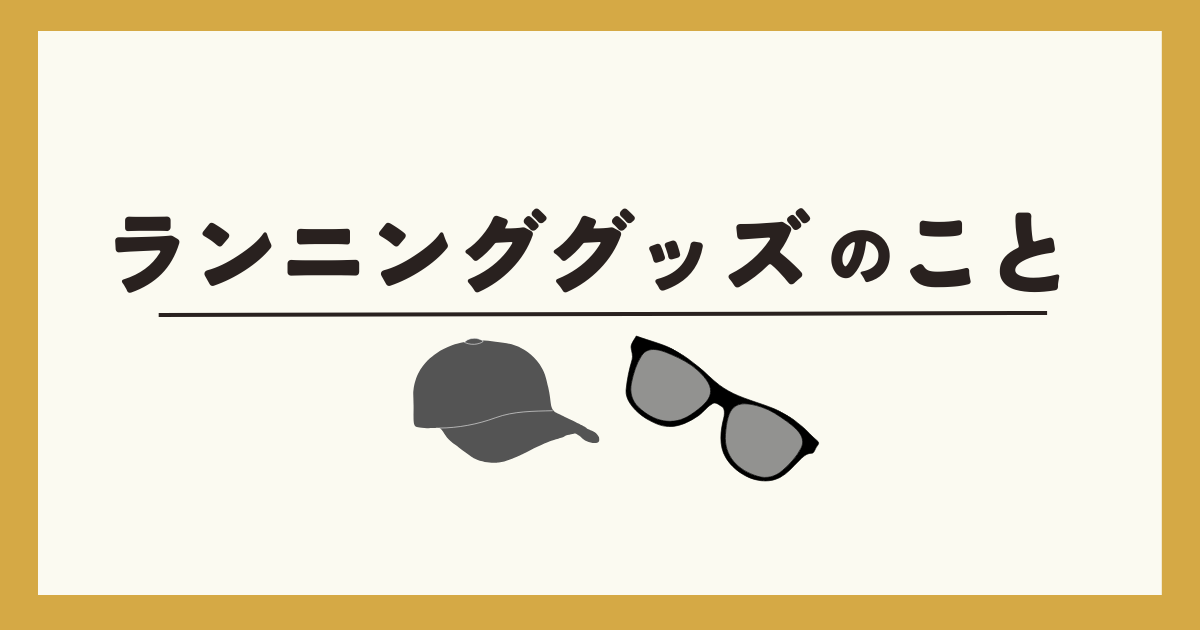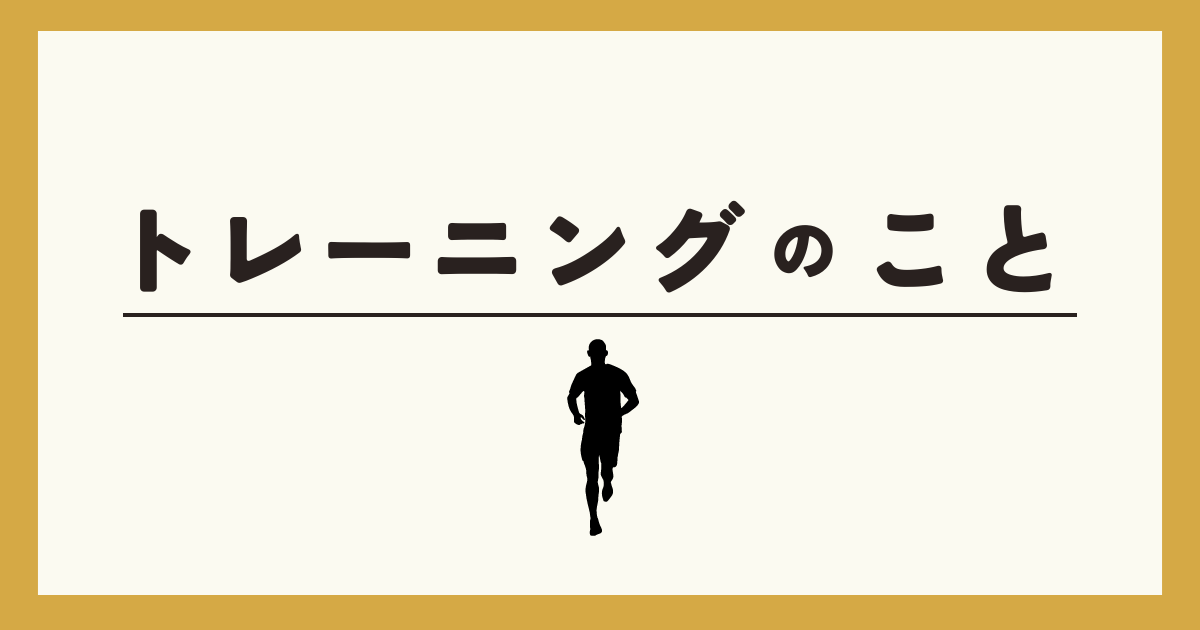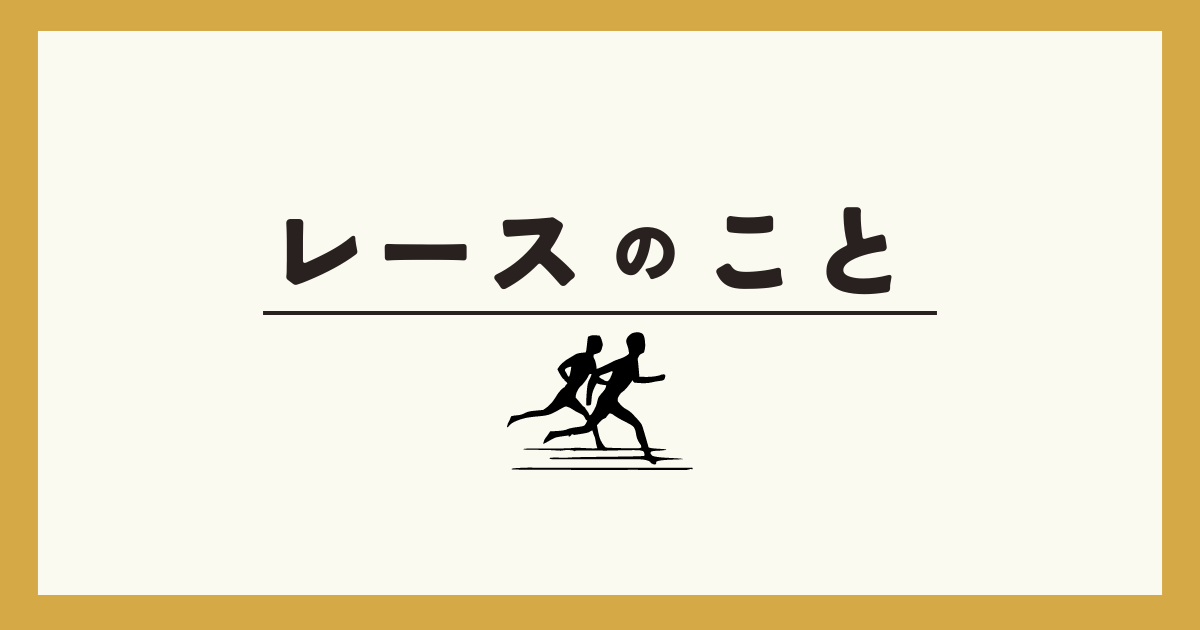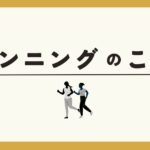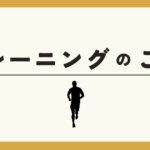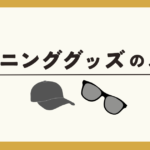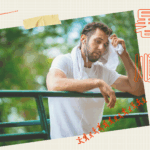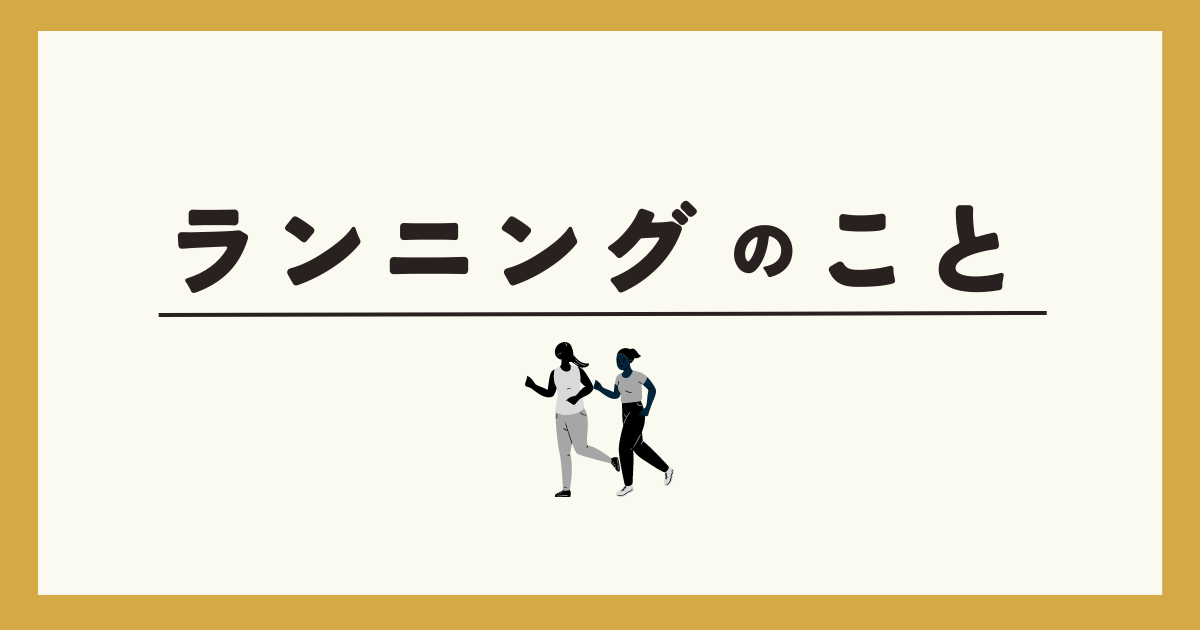
ゴールデンウィークの後にやってくる「あの感じ」
湘南の海沿い、江ノ島のシルエットが朝焼けに浮かぶ。波の音がリズミカルに響き、潮の香りが鼻をくすぐる。そんな絶好のロケーションで、二人の中年男性の裸足が砂浜を踏みしめる。笑顔でウォーキングしながら、時折軽快にジョグを挟み、たわいもない昔話に花を咲かせる。
その二人とは、私と私の大学時代の友人だ。一見、気まぐれに走っては歩き、走っては歩きを繰り返しているかのように見えるが、これが「WALK RUNS」のプログラムだ。この日は、休日の湘南の海を舞台に旧友と二人きりの特別プログラム。
都内からここに来た彼の目的は、単なるフィットネスではない。「五月病」を吹き飛ばすことだ。
「五月病」
耳にしたことがあるだろう。4月の新生活の興奮が冷め、ゴールデンウィークの連休が明けた5月、なんだか心が重い。職場や学校に向かう足取りが鈍り、朝起きるのが億劫になる。「自分、こんなんでいいのかな」と、理由もなく不安が募る。あの、なんとも言えない「モヤモヤ」だ。日本特有のこの現象は、医学的には「適応障害」や「軽度の抑うつ状態」と関連付けられることもあるが、診断名というよりは、季節の変わり目に心と体がズレる感覚を表す言葉だ。
「4月に昇格して5月になって、途端に調子悪くなったんだよね。連休前からプレッシャーや不安感で夜寝付けない日が多くて、連休でリズムが崩れたせいか、連休明けに仕事に戻っても頭がぼーっとする」と語るのは、大学時代の旧友ヤスヒロ(仮名)。
彼は、私の大学時代の駅伝部以外での数少ない友人だ。駅伝部の部員はほとんど体育学部だったが、私は文学部だったため一般学生の友人が何人かできた。彼は文学部の授業をジャージ姿で受ける私とつるんでくれた数少ない友人だ。
私が3月末で仕事を辞めたことをLINEで報告した時に、彼が職場で昇格した話を聞いた。それから1ヶ月が経ったGW中に「なかなか仕事がうまくいかない」という相談を受けていたので、GWが明けたら一緒にカラダを動かさないか?と誘ったところ快く湘南まで足を運んでくれたのだ。
おそらく彼の悩みは、多くの日本人が共感するものだろう。総務省の調査によれば、新入社員や人事異動等で環境の変わった社会人の約3割が5月に「仕事へのモチベーション低下」を感じると回答(2023年)。学生も例外ではない。新学期の緊張が解け、授業や人間関係のストレスがじわじわと積み重なるのだとか。
だが、ヤスヒロが今こうして湘南の海沿いで軽く汗をかきながら笑顔で私と話している姿を見ると、その「モヤモヤ」が嘘のようだ。なぜ、WALK RUNSのような軽い運動が五月病に効くのか? そこには、科学的な裏付けと、自然の風や誰かと身体を動かすことでの「マジック」がある。

五月病の正体は心と体の「ズレ」
五月病は、単なる「気の持ちよう」ではない。生理学的には、ストレス応答の仕組みが深く関わっている。
人間の脳には、ストレスに対処するための「HPA軸」(視床下部-下垂体-副腎軸)というシステムがある。新生活が始まる4月、環境の変化はHPA軸をフル回転させる。新しい職場や学校、人間関係、ルーティンの変化――これらはすべて、脳にとって「ストレス刺激」だ。HPA軸はストレスホルモンであるコルチゾールを分泌し、身体を「戦うか逃げるか」のモードに切り替える。
だが、このコルチゾールが問題だ。適度なら集中力やエネルギーを高めるが、慢性的に分泌されると、脳の「海馬」や「前頭前野」といった感情や記憶を司る領域にダメージを与える。結果、気分が落ち込み、意欲が低下し、疲れやすくなる。
これが、五月病の「ダルさ」や「モヤモヤ」の一因だ。東京大学医学部の研究(2022年)では、春の環境変化によるコルチゾール過剰が、20代の約4割で軽度の抑うつ症状を引き起こす可能性が示唆されている。
さらに、ゴールデンウィークの連休が拍車をかける。連休中は夜更かしや過度なリラックスで生活リズムが乱れ、セロトニンやメラトニンといった「気分を安定させる神経伝達物質」のバランスが崩れる。連休明けに急に「平日モード」に戻そうとしても、脳と体が追いつかない。これが、五月病の「ズレ」の正体だ。
では、どうすればこのズレをリセットできるのか? 答えの一つが、WALK RUNSのような「軽い運動」にある。
軽い運動の生理学的マジック
WALK RUNSは、特別なトレーニングプログラムではない。参加者は、自分のペースで歩いたり走ったりする。基本的には5分ウォーキング後、1分のジョギングと1分のウォーキングを交互に10分繰り返し、また5分のウォーキングで終わる。ただ、これは基本的なルールでアレンジは自由だ。10分ジョグして残りはウォークでもいい。本当に守るべきルールがあるとすると「苦しくない」。この「ゆるさ」が、五月病対策に最適な理由だ。
生理学的に、軽い運動が五月病に効くメカニズムは、主に3つある。
(1)セロトニンとエンドルフィンのブースト
ウォーキングやジョギングのような有酸素運動は、脳内のセロトニン分泌を促進する。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させ、ストレスを軽減する。ハーバード大学の研究(2020年)によると、週に150分の軽い有酸素運動(1日20~30分程度)で、抑うつ症状が30~40%改善する可能性がある。WALK RUNSの30~60分のセッションは、まさにこの「ゴールデンゾーン」にハマる。
さらに、運動はエンドルフィンも放出する。エンドルフィンは「天然の鎮痛剤」で、心地よい高揚感をもたらす。「歩いてたら、なんかスッキリした!」というこの感覚は、このエンドルフィンのおかげだ。
(2)コルチゾールのリセット
軽い運動は、過剰なコルチゾールを正常化する効果がある。スウェーデンのカロリンスカ研究所の研究(2021年)では、週3回の30分ウォーキングが、ストレスによるコルチゾール過剰を抑制し、HPA軸のバランスを整えると報告されている。
WALK RUNSは、ガチガチのランニングではなく「歩いてもOK」な点がポイント。激しい運動は逆にコルチゾールを増やすリスクがあるが、WALK RUNSのゆるいペースは、ストレスホルモンを抑えつつリフレッシュを促す。
(3)自然の癒しとBDNFの増加
スポーツジムなどの屋内ではなく外の空気を感じるというのも、WALK RUNSの秘密兵器だ。今回は海という特別な環境だが、普段の平塚総合公園や辻堂神台公園でも緑の芝生の上を、外の空気を感じながら動く。
自然環境での運動は、脳の「BDNF(脳由来神経栄養因子)」を増やす。BDNFは、ニューロンの成長や修復を促し、ストレスによる脳ダメージを軽減する。スタンフォード大学の研究(2019年)では、公園や海辺での30分ウォーキングが、都市部での同等の運動よりもBDNFを20%多く増加させ、気分改善効果も高いことが示された。緑のある公園や湘南の潮風は、ただの「雰囲気」ではない。脳を直接癒す生理学的効果があるのだ。
運動がくれる「小さな達成感」
「ここで、こうやってカラダ動かしたら、なんか『まぁいっか』って思えた。海もキレイで、心地よい汗がかけて、スッキリした。」ヤスヒロの言葉だ。
この「まぁいっか」という感覚こそ、WALK RUNSの五月病対策の核心だ。生理学的には、運動によるセロトニンやBDNFの増加が、ネガティブな思考を和らげる。だが、それ以上に、仲間とのゆるい交流や、負荷が高くなくてもプログラム後の「小さな達成感」が、心のズレをそっと修正する。
完璧なランニングフォームも、速いタイムもいらない。ただ、歩いて、走って、空気を感じればいい。それだけで、五月病の重い雲が少しずつ晴れていく。
科学とヒトとのつながり、SHONAN RUNSが目指すもの
WALK RUNSは、単なる運動プログラムではない。それは、湘南の地域的特性の「自由さ」と、仲間がくれる笑顔、そして自分の体が教えてくれる「動く喜び」を、五月病に悩む人々にも届けられるプログラムだ。
私がいつも話すのは「五月病だけじゃなく、たくさんの人が頭で考えすぎちゃう。だから、頭じゃなくて身体で感じてほしい。温まっていく自分の身体、外の空気、木々の香り、仲間とのたわいもない話。それが、結局一番効く」
生理学的には、ウォーキングやランニングはセロトニン、エンドルフィン、BDNFを増やし、コルチゾールを抑える「科学的に正しい」五月病対策だ。だが、それだけじゃない。歩いたり走ったりしながら、参加者が感じる「色々あるけど、まぁいいか」という瞬間。それこそが、SHONAN RUNSが目指すコミュニティのマジックだ。
あなたも「がんばらない」運動習慣へ
5月が終われば梅雨がやってくる。
新生活の疲れが、心と体をじわじわと蝕む季節だ。でも、諦める必要はない。スニーカーを履いて、外に出てみてほしい。一人で運動を始めるのが難しければ、WALK RUNSに参加してもいい。毎週末、同じ場所で待っている。
30分歩くだけでもいい。10分走れたら、それで十分だ。心地よい身体の疲れや汗が、あなたの五月病をそっと吹き飛ばしてくれる。
「ここに来ると、なんかリセットされるんですよね」と参加者が笑う。あなたも、そんな仲間に加わって五月病を蹴散らしてほしい。